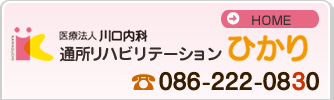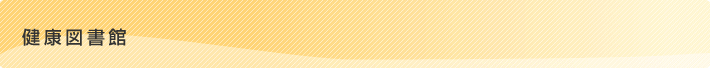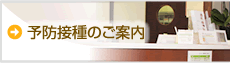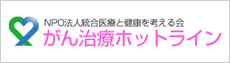咳が続く-難治性咳嗽(なんちせいがいそう)・慢性咳嗽
2025.06.27
医療用語では咳(せき)をことを咳嗽(がいそう)といいます。
ここでは咳嗽よりも、皆さんにとって身近な「咳(せき)」という言葉をできるだけ使いながら説明していきます。咳は気道内に痰(たん)があるときや異物が入ったときに反射的におき、体を守る自然な反応です。しかし、そういった一時的な反応ではない場合は受診をお勧めします。
咳の症状は、発熱や腹痛と並んで多い受診理由です。誰もが経験したことがある症状でしょう。
診断
当院ではまず問診で
・咳が出始めた時期(何週間続いているか)
・咳が出やすい時間帯
・咳に痰がからむかどうか
乾性咳嗽:痰がからまないコンコンといった咳
湿性咳嗽:痰のからんだ咳、ゴボゴボといった咳
・発熱や悪寒などの症状を確認します。
次に胸部の聴診で原因特定につながる音があるかないかを聴取します。必要な場合は肺機能検査、胸部X線検査、血液検査、抗原検査などの各種検査を行います。
これらにより、つぎのことを診断していきます。
・発症後3週間以内の急性咳嗽(きゅうせいがいそう)
-風邪(普通感冒)などの感染症の疾患による咳
-風邪以外のウィルス感染症の疾患による咳
-気管支炎、肺炎による咳
・3週間以上の遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)、8週間以上続く慢性咳嗽(まんせいがいそう)
-花粉症による咳
-アトピー性の咳
-感染後咳嗽症
-咳喘息
-マイコプラズマ
-百日咳
-副鼻腔気管支症候群
-胃食道逆流症
-肺癌や間質性肺炎
-結核
-喫煙、受動喫煙、慢性閉塞性肺疾患
-真菌症
-薬剤性(ACE阻害薬、β遮断薬)
-気胸、気道異物
-心因性咳嗽、原因不明の咳
治療方法
咳症状の原因疾患が判明した場合は、咳や痰を抑える薬剤投与や疾患に合わせた治療を行います。
しかし、「精査でも原因が不明で、治療しても8週間以持続する咳」は難治性咳嗽(なんちせいがいそう)と呼ばれています。
当院では問診と診察や種々の検査により診断し、診断に基づき疾患に対する西洋医学に基づく治療を行う一方、疾患によりもたらされる症状や体質や体力など体調をもとに漢方医学に基づく治療も選択できます。特に慢性の咳に対する漢方薬が有効であることが日常臨床でたびたび体験します。
漢方薬を使用する際は咳や痰の性状を把握することが重要で、乾性咳嗽においては滋陰降火湯湯(じいんこうかとう)などを用います。湿性咳嗽に対しては滋陰至宝湯(じいんしほうとう)、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)などを使用します。また高齢者などの慢性閉塞性肺疾患(COPD)には清肺湯(せいはいとう)や五虎湯(ごことう)も有用です。
[ 健康図書館一覧へもどる ]