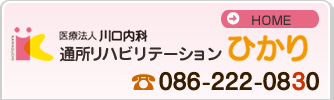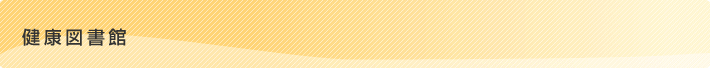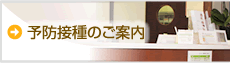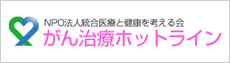更年期障害の症状と治療
2025.06.28
厚生労働省のサイトを参考にして作成
更年期障害の症状
更年期障害のおもな症状は次のようなものです。
・のぼせ・ほてり、発汗 *ホットフラッシュとよぶことがあります
急に顔が熱くなったり、汗が止まらなくなったりする症状。上半身ののぼせ、ほてり、発汗などが起こる、更年期障害の代表的な症状です。「上半身だけ暑くて、」「冬でも突然、頭と顔に大汗をかく…」など、更年期世代の女性に多い悩みです。
・冷え
更年期障害による冷えの場合は女性ホルモンの影響によるものが多く、意外に思われると思いますが、ほてりや汗が出るのも冷えの一種です。西洋医学では病気ととらえにくい冷え症も、漢方では治療の対象です。「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」「温経湯」「桂枝茯苓丸」「加味逍遥散」などが女性の冷え症によく使われる漢方薬です。
・イライラ
イライラは、日常生活上、誰にでも認められる感情です。特に更年期の影響で、女性はこれらの感情が男性より起こりやすい特徴があります。「自分自身で精神コントロールが難しい」「日常生活に障害が出ている」ような、イライラを感じていることが多い場合は、医療の援助が必要です。まずは更年期障害なのか、甲状腺機能障害などの他の疾患なのかを検査しましょう。
・不眠
不眠は、「入眠困難(寝つきが悪い)」「中途覚醒(眠っても、よく目を覚ます)」「早朝覚醒(早く目が覚めて困っている)」に分けられます。
また、睡眠時無呼吸症候群があると、よく寝た感じがしない、いびきをかく、呼吸が止まるなどの症状が出ます。睡眠時無呼吸症候群では、終夜睡眠ポリグラフ検査が有効です。治療に睡眠薬などの薬物療法があります。また漢方治療も有効な場合があります。
・抑うつ、無気力
うつ病ほどはっきりした落ち込みや日常生活のひどい支障はないものの、なんとなく憂うつで悲観的に考える状態がダラダラと長く続きやすい状態が更年期障害の時期にはよく見られます。ほかにも、甲状腺などのホルモン疾患にともなううつや、一部の薬剤の影響で起こるうつ、慢性・難治性の病気に罹患したことにより起こるうつもあります。うつの診断は、国際的に使用されているICD-10やDSM-5という診断基準が用いられ、症状や経過と照らし合わせて行います。
・めまい・耳鳴り
更年期世代の女性には「疲れるとめまいや耳鳴りがしてきます」という訴えが多くあります。更年期障害による不眠からのストレスでめまいを発生することもあります。検査をしても特に病気の異常がない更年期障害の症状として「めまい症」があります。更年期障害のめまい症の場合は、女性ホルモンや漢方薬など更年期障害の治療が有効になります。
・頭痛
頭痛の診断は、まずクモ膜下出血、頭蓋内出血、脳腫瘍のような緊急性のある病気で生じる頭痛かそうでないかを判断します。緊急性のある病気の場合は、突然「今までに経験したことのない」激烈な痛みがあり慢性頭痛とは明らかに異なっていることがほとんどです。慢性的な頭痛を起こす器質的な疾患としては、副鼻腔炎、下垂体炎、低髄液圧症候群、髄膜炎、硬膜炎、睡眠時無呼吸などがあります。更年期障害で発生するホルモンバランスの変調や睡眠の質の悪さから頭痛になることがあります。
緊張性頭痛は、頭痛の大半を占める、いわゆる肩(首)こりによる頭痛で、首筋の痛みや非回転性のめまい、軽い気持ち悪さや嘔吐をともないます。緊張性頭痛は筋肉疲労ですから我慢するほど症状は悪くなります。鎮痛剤のほか、熱いタオルで頸部を暖める、ストレッチをまめにするなどが効果的です。良質の睡眠をとることも必要です。
片頭痛の場合は鎮痛薬は効かず、スマトリプタン製剤が効果的です。
・膝痛、腰痛
更年期世代になると、ひざや腰の関節の痛みを訴える女性が増えてきます。骨、関節や軟骨も、エストロゲンに守られてきています。更年期にエストロゲンが減少することで、関節の痛みなどの症状が出やすくなります。更年期障害による膝痛、腰痛の場合は更年期障害の治療で痛みが軽減するケースもあります。
そのほかにも次のような症状があります。
・動悸
・息切れ
・皮膚の乾燥、かゆみ、湿疹
・疲労感
加齢により卵巣から分泌されるホルモン(エストロゲン)の分泌が減少します。このホルモン分泌減少はすべての女性に発生しますが更年期障害の程度はひとによってさまざまです。
更年期は人によって差がありますが日本人女性平均では50歳を挟む前後10年間(45歳~55歳)が更年期になります。この年代は加齢による身体機能低下と仕事や人間関係の変化が起きることも多く、心的ストレス、性格的なものも更年期障害の症状の程度に影響します。
人によってたいした症状を感じないまま更年期を過ぎる場合もあれは、仕事の継続や日常生活に支障をきたすほどひどくなる場合もあります。
更年期障害の診断と治療
更年期障害は患者さん自身が自覚している症状をまとめることから始めます。
・ほてり、発汗/・冷え/・イライラ/・不眠/・抑うつ、無気力/・めまい/・耳鳴り/・頭痛/・動悸/・息切れ/・皮膚の乾燥、かゆみ、湿疹/・腰痛、関節痛、肩こり/・疲労感の症状の有無と程度です。
またデータ血液中のホルモン濃度測定を行うことも更年期の診断に有効です。特に更年期障害と思い込んで見逃しやすい疾患として糖尿病、甲状腺機能低下症、高血圧、メニエール病、手指関連疾患など、50歳近辺で頻度が多くなる疾患があります。今、現れている症状が更年期障害によるものか、他の疾患によるものかの診断を受けておきましょう。
治療には、
ホルモン剤
漢方薬
エクオールやプラセンタ注射
自律神経調整薬
睡眠剤
向精神薬
など症状によりさまざまな方法があります。
当院では診断により、漢方薬のみでの治療とホルモン剤などとの併用治療も行っています。
日本における漢方医学は、その昔、中国から伝わった伝統医学がルーツですが、日本の風土や日本人の体質に合うように改良され、長い年月をかけ、効果や安全性が確かめられた日本独自の医療で海外でも「KAMPO」として知られています。
また、日本の漢方医療は、西洋医学を学んだ医師が西洋薬と一緒に漢方薬を処方します。医師の処方箋があれば、基本的に医療用漢方薬は、健康保険が使えます。
[ 健康図書館一覧へもどる ]