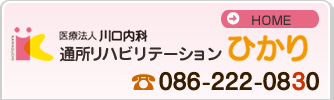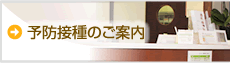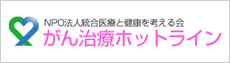帯状疱疹の特徴は「痛み」です
帯状疱疹が命に関わることはほとんどありませんが、苦痛と不安は相当なものです。
帯状疱疹の症状はこのように進みます
経過や痛みの程度には個人差がありますが、身体の右側、または左側どちらか一方に、
・ピリピリ、チクチク、ズキズキといった神経痛が出ます
・1週間程度で痛みがある部分に赤い斑点が現れます
・赤い斑点内に水ぶくれができ、水ぶくれが破れてただれた状態になります
・かさぶたになり、徐々に症状が治まる。
以上の経過をたどり症状がおさまるのに4週間~8週間程度を要します。



ただし、皮膚の症状が治った後も、痛みが残ることがあります。特に痛みが3か月以上続く場合は「帯状疱疹後神経症」と呼びます。人により痛みの表現は異なりますが「刺すような痛み」「焼けるような痛み」が数年にわたって続くことがあります。特に50歳以上で帯状疱疹を発症した場合は約2割が帯状疱疹後神経症になると言われています。
注意が必要な合併症-目や耳に帯状疱疹が現れるときは注意が必要です。重症化すると視力低下、失明、顔面神経麻痺など重い後遺症が残ることがあります。
帯状疱疹がどのような病気なのか、なぜ発症するのかを知りましょう。敵を知れば百選危うからず。
なぜ帯状疱疹が発症するのか 帯状疱疹の原因
あなたは「水ぼうそう」にかかりましたか。
多くの方は子どもの頃に「水ぼうそう」にかかり、一週間ほどで治っています。
「水ぼうそう」が治る仕組みは他のウイルス性疾患と同様で、「ウイルス」に対する「免疫」が「ウイルス」をやっつけていくからです。このとき体内では「水ぼうそうウイルス」を退治するため緊急かつ大量に免疫細胞が作成されます。

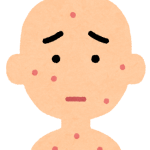

「水ぼうそうウイルス」は大量の免疫細胞の攻撃を受けて、次々と減少していきます。その時、少数の「水ぼうそうウイルス」は生き残りをかけて体内の「神経節」という部分に隠れます。
神経節に隠れた「水ぼうそうウイルス」は「免疫」の防御網から逃れるため長年にわたって神経節に潜み続けます。そして加齢や過労、ストレスなどで免疫が低下すると、潜伏していたウイルスは神経節の神経細胞の奥から体内の神経を経由して体表に出てこようとします。そのため
まず神経が痛み(神経の炎症)
その後皮膚症状(皮膚の炎症)が発症する
という順序で帯状疱疹は進行します。
日本の成人の9割以上がこのウイルスを保有
日本人の多くは幼少期に水ぼうそうに罹患しているため、日本の成人の9割以上がこのウイルスを保有しています。そのため長寿社会となった日本は加齢による免疫低下の発生リスクが高まり80歳までに3人に1人が帯状疱疹を経験すると言われています。
特に帯状疱疹患者の約7割は50歳以上の方で、50歳以上から発症数が急増することがわかっています。
また、若くてもストレスや他の疾患で健康状態が変化し免疫が低下すると帯状疱疹を発症します。

*治療方法と予防方法も進化しています-もう少し読み続けて下さい*
帯状疱疹の治療方法
抗ウイルス薬、鎮痛薬、外用薬、神経ブロックを症状に応じて組み合わせます。
抗ウイルス薬
治療の主力になるのは抗ウイルス薬です。帯状疱疹の原因であるウイルスの増殖を抑える薬です。通常は内服薬を用いますが、重症の場合は点滴することがあります。
抗ウイルス薬は効果が現れるまでに2~3日かかります。飲み始めてすぐに効果が現れなくても医師の指示通りに服用して下さい。
抗ウイルス薬は水ぼうそうウイルスが皮膚や神経を破壊する前に用いることがポイントです。そのためにはできるだけ早期に治療を開始することが大切です。
特に50歳以上で子どもの頃に水ぼうそうに罹ったことのある方は、帯状疱疹の症状が出たら、直ぐに診断を受けることをお勧めします。抗ウイルス薬が高い効果を発揮するのは帯状疱疹発症後、2日目が目処です。3日目以降だと効果を発揮できないことがあります。

鎮痛薬
痛みが特徴の病気です。まずは痛みを和らげ、治療に取り組める精神と体力を保ちましょう。また痛みが強く神経を痛めてしまうと、帯状疱疹の皮膚症状が治まった後も痛みが残るリスクが高くなります。
非ステロイド系の消炎鎮痛薬や神経障害性疼痛治療薬を用いますが、痛みが激しい場合や麻痺が見られる場合はステロイド内服薬を使うことがあります。

外用薬(塗り薬)
帯状疱疹による皮膚のただれに対して、細菌による二次感染を防ぎ、皮膚を保護したり皮膚の再生を促したりします。

神経ブロック
神経の周りに直接、局所麻酔を注射する方法です。痛みがとても激しい場合に行うことがあります。必要があれば専門医を紹介します。
帯状疱疹を予防するワクチンがあります
多くの人が子どもの時に感染する水ぼうそうウィルスが帯状疱疹の原因になっていますので、日本人成人の90%以上は帯状疱疹の原因となるウィルスが体内に潜伏しています。
人生100年と言われるほどの長寿社会となった現代では、80歳までに約3人にひとりが帯状疱疹を発症するようになりました。これは加齢による免疫力の低下が主な原因と考えられています。
また加齢による免疫力低下以外にも、疲労、ストレスや糖尿病、がんなどの免疫力が低下する病気が原因になることもあります。
そこで帯状疱疹を予防するためのワクチンが開発され、日本でもワクチン接種できるようになりました。このワクチンは注射で2回接種します。1回目を接種後、2か月程度後に2回目を接種します。
インフルエンザワクチン接種と同じく、病気治療のための注射ではなく、予防になりますので保険診療ではなく、自由診療扱いになっています。インフルエンザ予報接種と比較すると高価(22,000円×2回)ですが、帯状疱疹への高い予防効果が期待できます。もちろん他のワクチンと同様、完全な予防を保証するものではありませんが、帯状疱疹が発症した場合の症状の軽減効果、特に帯状疱疹後神経痛、目の視力低下をもたらす合併症まで考慮すると50歳以上の方には接種をお勧めします。
このワクチンはインフルエンザワクチンのように毎年、接種が必要なものではなく、50歳以上が接種した場合の効果は長期にわたり有効とされています。インフルエンザワクチン接種が毎年必要なことを考慮すると、長期的には経済的に優れたワクチンとも言えます。
帯状疱疹ワクチンには病原性をなくしたウィルスの一部を成分とした不活性化ワクチンと病原性を弱めたウィルスそのものを成分としたワクチンがありますが、当院が選んでいる帯状疱疹予防ワクチンは不活性化ワクチンであるグラクソ・スミスクライン社「シングリックス」です。

院長:川口光彦
帯状疱疹予防ワクチンの接種対象年齢50歳以上ですので、患者さんにお勧めする前に自分自身で接種致しました。このワクチンが長期にわたり有効であることを体験中です。
帯状疱疹のQ&A よくある質問
Q.お風呂にはいってもよいですか?(帯状疱疹とお風呂)
お風呂に入った方が痛みが和らぐことが多いようです。石けんの使用もできます。ただし、刺激のあるタオルでゴシゴシ肌を洗うことは避けて下さい。
入浴後は清潔なタオルで軽く押さえるように水気を取りましょう。外用薬を処方されている場合は入浴後に塗布して下さい。
Q.帯状疱疹は人にうつりますか?
帯状疱疹そのものは触って他の人にうつることはありません。ただし、水ぼうそうにかかったことのない人には水ぼうそうとしてうつることがあります。水ぼうそうにかかっていない幼児や妊婦さんにはできるだけ接触しないようにして下さい。
Q.消毒が必要ですか?
必要ありません。お風呂やシャワーも使えます。外用薬をガーゼに伸ばし貼付している場合は、シャワーをあて、濡らしてからはがすと、あまり痛みを感じずはがせます。
Q.仕事はしてもよいですか?
病気ですので休養をとることが大切です。仕事を行う場合は、無理がない程度に抑えて下さい。
Q.湿布薬で冷やしてもいいですか?
個人差がありますが冷やすと痛みが増すことがあります。また、かぶれを起こすことがあるので、処方されたもの以外の使用はお勧めできません。
Q.使い捨てカイロで温めてもいいですか?
心地よい程度に暖めると痛みが和らぐことが多いようです。ただし、使い捨てカイロなどを直接肌に貼るのはヤケドを起こす原因になりますので避けて下さい。
<参考資料:帯状疱疹といわれたら6版/各種医療関係者用情報資料>
帯状疱疹ワクチン2種の違いをまとめました
帯状疱疹ワクチンには従来の「弱毒化生帯状疱疹ワクチン」いわゆる生ワクチンと2020年から使用できるようになった「乾燥組換帯状疱疹ワクチン」シングリックスがあります。(シングリックスは薬剤の固有名です)
2つのワクチンの違いを表にまとめてみました。
|
弱毒化帯状疱疹ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 |
乾燥組換帯状疱疹ワクチン シングリックス筋注用 |
|
| ワクチン株・抗原 | 弱毒性水痘ウイルス | VZV糖タンパクE(gE) |
| 接種回数 | 1回 | 2回(通常2か月間隔) |
| 効果持続 | 8年間 | 現時点で9年以上(追加調査実施中) |
| 有効性 | 60歳以上の健康成人を対象とした臨床研究で平均3.13年の観察期間で、帯状疱疹発症率は51.3%減少、重症度スコアは61.1%減少、帯状疱疹後神経痛は66.5%減少。50~59歳の健康成人を対象とした臨床研究では平均1.3年の観察期間で帯状疱疹発症率は69.8%減少 | 50歳以上で平均3.2年の観察期間で帯状疱疹予防効果97.2%減少。帯状疱疹後神経痛の発症無し |
| 副反応 | 接種後50.6%に副反応 注射部位の紅斑44.0%、掻痒感27.4%、熱感18.5%、腫脹17.0%、疼痛14.7%など。 | 注射部位副反応(2回接種合計)は80.8% 疼痛78.0%、発赤38.1%、腫脹25.9%など。全身副反応は64.8%、筋肉痛40.0%、疲労38.9%、頭痛32.6%など。 |
| 水痘予防の適応 | あり | なし |
| ブースター目的のワクチン再接種 | 追加接種の制限なし。時間とともに予防効果が減弱するため追加接種が必要(おそらく8~10年後には再接種が必要) |
追加接種は必要なし。 |
| 妊婦への接種 | 禁忌 | 禁忌ではないが接種時期をおくらせるよう勧告 |
| 適用年齢 | 50歳以上 | 50歳以上 |
| アジュバント | なし | あり ASO1s含有 |
*アジュバントとは……ワクチンと一緒に投与して、その効果(免疫原性)を高めるために使用される物質のことです。
上表の作成のために参考にした文献、資料:日医雑誌第149巻第7号特集ヘルペス感染症2020帯状疱疹予防ワクチン/グラクソ・スミスクラインの医療関係者向情報サイト